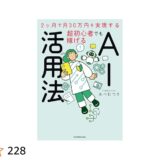※このページにはPRが含まれています
はじめに
新聞記者として30年のキャリアを持つ私が、webライティングの世界に足を踏み入れたとき、最も戸惑ったのが「SEO(検索エンジン最適化)」という概念でした。
検索結果の上位に表示されるためのテクニックや戦略が存在し、それがウェブ記事の評価を大きく左右するという事実は、紙媒体での経験しかなかった私にとって新鮮であり、同時に違和感も覚えました。
検索されるためのキーワードとはいえ、同じ単語を繰り返すのは、新聞記事的には単調さが増し、文章評価のマイナスになります。
こういった課題意識から、今回はSEOが記事の「正しさ」や「真実性」にどのように関与しているのか、そして新聞記事との違いを通じて見えてくる問題点について考察してみたいと思います。
SEOと新聞記事の評価基準の違い
新聞記事は、事実に基づいた情報を読者に提供することが使命です。記者は取材を重ね、裏付けを取り、情報の正確性を何よりも重視します。読者は、その信頼性をもとに新聞を購読し、記事を評価します。
一方、SEOは検索エンジンに評価されることを目的としています。検索エンジンは、ユーザーの検索意図に合致したコンテンツを上位に表示するため、キーワードの使用頻度や配置、ページの読み込み速度、モバイル対応など、さまざまな技術的要素を評価基準としています。
書き手が読者ではなく検索エンジンの方ばかり向いているような文章を目にすることがある。
読者にとってのメリットよりも検索エンジンに好まれることが優先される傾向にある。これを勘違いすると、結局、web文章からの読者離れが加速するのではないだろうか。
結果的に会話で分かりやすく表現する動画に人気が集中することになる。
新聞記事とSEO記事では、評価の基準が根本的に異なる。新聞記事は「真実性」、SEO記事は「検索エンジンの評価基準への適合性」が重視されるのです。
長期保証付きで常時400種4000台の中古PCを販売【PC WRAP】SEO至上主義のリスク
SEOを重視するあまり、記事の内容が検索エンジンに最適化されすぎてしまい、読者にとっての「読み応え」や「信頼性」が損なわれるケースが増えています。
例えば、特定のキーワードを過度に繰り返すことで文章が不自然になったり、情報の裏付けが不十分なまま公開されたりすることがあります。
また、検索エンジンのアルゴリズムは常に進化していますが、完全に人間の判断基準と一致するわけではありません。そのため、SEO対策だけに頼った記事は、読者の信頼を得ることが難しくなる可能性があります。
ハイブリッド方式の必要性
このような状況を踏まえ、私は「新聞記事の真実性」と「SEOの技術的最適化」を融合させた「ハイブリッド方式」が必要だと考えています。
具体的には、以下のようなアプローチが考えられます:
- 事実確認の徹底:情報の出典を明確にし、裏付けを取ることで、記事の信頼性を高めます。
- 読者目線のコンテンツ作成:読者が求める情報を的確に提供し、分かりやすい表現を心がけます。
- 適切なSEO対策:キーワードの自然な配置や、ページの読み込み速度の最適化など、検索エンジンに評価される要素を取り入れます。
このように、ジャーナリズムの精神を持ちながら、SEOの技術的要素を取り入れることで、読者にとって価値のあるコンテンツを提供することが可能になると考えています。
まだ模索途中ではありますが、従来の新聞記事の手法だけではもはやデジタルメディア時代には付いていけない。
そうは言っても、完全にSEОだけに頼りすぎても面白くない。その塩梅をどの地点に持っていくか、試行錯誤し続けるしかないと思っています。
結論
SEOは、ウェブ上での情報発信において重要な要素であることは間違いありません。
しかし、それだけに頼るのではなく、情報の正確性や読者への配慮といったジャーナリズムの基本的な姿勢を忘れてはならないと感じています。
今後も、新聞記者としての経験を活かしながら、SEOと真実性のバランスを追求したコンテンツ作りを目指していくしかないと思っています。
次回へ
次回の「web文章道」シリーズ第3弾では、具体的なSEO対策の方法について、新聞記者の視点から考察していく予定です。引き続き、ご期待ください。
web文章道第1弾は↓