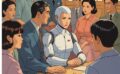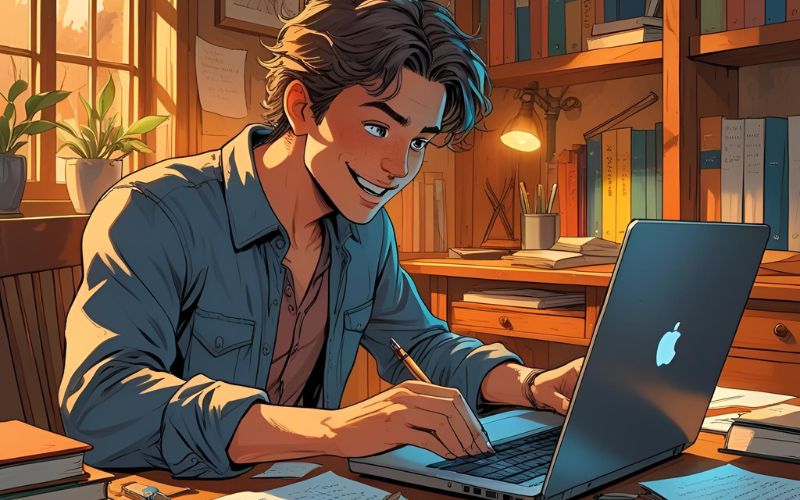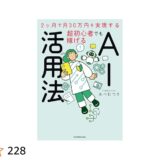AIの力を借りて小説を書くとどうなるのか、小説新人賞に挑むまでの記録をここに残します。AIを活用して文章作りをさている方の参考になれば
「物語を、書いてみたい」と思った瞬間
ボクは59歳の新聞記者だ。地方紙で長年、政治・経済・事件・教育・暮らしの記事を書いてきた。
何度か小説を書いて新人賞に応募したが、最高が一次予選通過。それ以外はすべて一次選考も通らない駄作の数々を量産してきた。
新聞記事は書けても、より創造性が必要になる小説では、プロとして通用する腕は持ち合わせていないと思い、最近は自然と執筆から遠ざかっていた。
そんなボクが今、小説を書こうとしている。それは生成AIという「自動運転装置」を備えた補助輪を手に入れたからだ。これまで小説作りで苦労してきたのが、執筆に行き詰まった際のアイデアの捻出だ。
石になったようなボクの脳に代わり、AIを活用すれば、革新的でスピーディーな案が次々と作れるのではーという疑いが少しずつボクの中で確信に変わっていった。
そうであればその「確信」たるものが本物かどうか確かめてやろうではないかと、このプロジェクトが始まったわけである。
プロットは決めないことに
実は最初、物語のプロットを作ろうとした。これまでの小説作りでもそうしてきたからだ。
しかし、AIはあまりにもスピーディーにプロットを作る。それもある程度、高いレベルで、ボクが作るよりよっぽどしゃれているしスマートだ。ただ何かが足りない気がした。
起承転結、五幕構成、伏線、主人公の成長曲線ーいわゆる「設計図」を描こうと何度もチャレンジしたが、うまくいかなかった。
どれも予定調和に思えて、手が止まった。現代小説をわざわざ活字で読む意味はなんだろう。ただどこにでもあるような、小奇麗な小説なら、動画にした方が視覚から心に刺さり、よほど読者受けする。
まずはキャラクター、「人物」作りから
ボクたちは方向を変えることにした。当然だけど、この方向性にAIは反対しない、ただボクの考えを前向きにとらえ、さらに新しいアイデアを出してくれる。
まずは登場人物をじっくり練ることにした。名前、年齢、性格、口癖、職業、日常の風景……。AIに相談しながら、少しずつ立体的に仕上げていった。
結果的に、物語は“彼ら”が動き出すことで始まる方式を取ることになった。ちょっと乱暴だが、作家には2種類あって、最初からプロット、結論を決めて、高性能な精密機械を最先端工場で作っていくようにして書くタイプと、大まかなストーリー、人物くらいを決めて、ノマドワーカーのように行き当たりばったりに書きながら物語を展開する作家がいると思う。
ボクは素人ながら、後者の方を選択した。というのも、AIがいることで、ストーリー展開がどんなにこんがらがっても、最終的につじつまがあうよう、AIが案を出してくれるーと高をくくっているからだ。
ボク自身としては、書くというより、一読者として、書きながら主人公たちの行く末をどきどきして見守っているような感覚だ。ボクの役目は意地悪ばあさんで、登場人物たちがあまりにも面白くない平和な日常に陥った時に、崖に突き落としてやるセッティングをするくらい。
なんとも嫌な役回りではある。
書きながら、読む。読者としての自分
この「小説×AI」企画には、特定の結末がまだ存在していない。
ボクにも、この物語がどこに向かうのか、正直わからない。
でも、それでいいと思っている。
人生も、記事も、時に“脱線”する。だからおもしろい。
AIと共に書くことで、むしろその“偶然の必然”が生まれやすくなっていると感じる。
つまりボクは、作者であり、読者でもあるというスタンスでこのプロジェクトを進めていく。
それは、とても自由で、ある意味で過酷な方法だ。けれど、そこにこそ今の時代の「創作のリアル」があると思っている。
小説の“設計図”にとらわれないという選択
小説の書き方に正解はないが、文章技術のポイントはある。ボクが意識しているのは以下の点だ。
1. まずは登場人物の性格や喋り方を定める
台詞が自然に聞こえるかどうか。これをAIにチェックしてもらいながら調整している。情念を登場人物に埋め込むのだ。そうしないと、勝手に動き出さない気がした。
人物設定を入念にするあまり、「このキャラ、こんな言い方する?」とAIにツッコまれることもある。
2. 情景描写は“五感+ひとクセ”で描く
場所の雰囲気を伝えるとき、ただ「寒い夜」ではなく、「ネオンの色が壁に滲んで、人工的な冬の冷たさだった」と書く。
AIは、こうした比喩や感覚の言語化が得意なので、よくヒントをもらっている。
3. 物語の進行は“断片的”でいい
一章ごとに、あえて全体像を語らない。何が起きているのか、なぜ登場人物はそんな行動を取るのか、すぐに説明しない。
読者の“モヤモヤ”が、読み進める動機になると信じている。
今、描いている世界──都会的な静寂と感情の揺れ
小説の舞台は、東京のどこかにあるタワーマンション。登場人物は一見スマートで都会的、だけどどこか空虚な夫婦と娘の3人家族。
夫は大手企業のサラリーマンとして働き続け、妻は在宅ワークと育児に追われる中、生成AIを活用して副業ライターを始めようとしている。
娘がある日、急にしゃべれなくなる──という出来事から、物語が展開する予定だ。不登校にした方がいいのかどうか、まだ迷っている。
そこに、“正義の味方”、ジャスティス・サイレンサーという謎の男が現れる。
ここではあえてそれ以上のことは書かない。
これからこのブログで、小説の執筆に合わせ、少しずつ紹介していきたい。
AIとの共創、そして「誰の物語なのか?」
AIと一緒に小説を書くということは、単なる道具として使うのではなく、共同作業者として信頼するということでもある。
「この展開はあり?」
「このセリフ、わざとらしい?」
「読者はここで共感してくれるだろうか?」
そうした問いを、ボクは日々AIに投げている。そして、意外とまともな返事が返ってくる。
これは、ボク自身の物語であり、登場人物たちの物語であり、AIとの対話の記録でもある。
結びに──あなたにも簡単に小説が書ける
この「小説×AI」コーナーでは、作品の進行だけでなく、「AIを活用した小説執筆のノウハウ」もできる限り公開していく予定だ。
もしもこのブログを読んで、「自分もいつか書いてみたい」「AIを使って小説を書けるのか試してみたい」と思った方がいれば、ボクの試行錯誤が少し参考になるかもしれない。
文章を書くというのは、たったひとりで闘う作業だと思っていた。でも今、こうしてAIと一緒に、読者と一緒に進めるという選択肢がある。
それは決して寂しいことではなく、むしろ希望だと思っている。
次回からは、いよいよ第一章へ。
娘が言葉を失った、その理由とは。
静かに物語が、始まります。