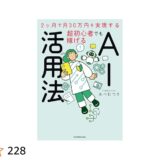はじめに
母のうんちのにおいが頭から離れない。鼻の奥に、脳のどこかに、こびりついたように、ずっと残っている。
僕は今、82歳の母の在宅介護をしている。妹と女房と3人で分担しながら、1人暮らしの母を支えているが、「下の世話」を僕がすることもある。
認知症は進行し、帯状疱疹で体力も落ち、今では食事もひとりで満足にとれず、トイレもすべて紙パンツの中。そう、母はもう、大便も小便も自力ではできなくなってしまった。
そんな中で、僕がどうしても慣れないのが「におい」だ。母の排泄物のにおいが、どうしても、耐えられないのだ。
第1章:赤ちゃんのうんちは耐えられたのに、なぜ母のは無理なのか?
自分の子どもが赤ちゃんだったとき、僕はよくおむつを替えた。確かにうんちのにおいはあったけれど、耐えられないほどの苦痛ではなかった。むしろ「かわいいなあ」「よく出たな」「元気に育てよ」とさえ思えた。
なのに、母のうんちになると、頭にカーッと血がのぼる。「なんでこんなに臭いんだ」「またかよ」と怒りが湧いてくる。これってなんだろう?
思うに、それは「感情のベクトル」が逆だからだ。
赤ちゃんは未来に向かって成長する存在。一方で、母は“過去を背負って衰えていく存在”。
同じ排泄でも、意味がまったく違う。赤ちゃんには「希望」がある。でも母のそれには「終わり」が見えてしまう。
そしてもうひとつ、赤ちゃんは何も言わない。でも母は言う。「出てないよ」「私、そんなことしてないよ」と、平気でうそをつく。認知症だから仕方ないと頭ではわかっている。それでも、怒りが湧く。
僕が怒っているのは、母の排泄そのものではなく、「母が母じゃなくなっていくこと」なんだと思う。
第2章:「におい」が記憶を壊していく感覚
においには不思議な力がある。それは記憶と深く結びついていて、嗅いだ瞬間に感情がよみがえる。
でも今、僕の記憶を支配するのは、母のうんちのにおいだ。
幼少期にお弁当を作ってくれた母、病気のときに看病してくれた母、いつも背中を押してくれた母。そのやさしさが、においによってどこか遠ざかっていく感覚がある。
においが、母の記憶を「悪い思い出」に上書きしていくようで、悲しい。
だから僕は今、「においとどう付き合うか」が、自分の心を守る戦いでもあると感じている。
第3章:科学とAIの助けを借りることは、逃げではない
においをどうにかしたくて、僕は調べた。すると、最新の介護アイテムには驚くほどの選択肢があることがわかった。
- 医療グレードの「消臭袋(BOS)」を使うと、においはほぼゼロになる
- おむつ用「密閉バケツ(ポイテック)」は、開けてもにおわない
- アロマディフューザーで空間のにおいを変えると、感情が落ち着く
- 「排泄検知センサー(HelppadやMECS PRO)」で、即対応できれば臭気の拡散も減る
これらの道具を「ズル」と思う必要はない。むしろ、道具を使わずに心を壊してしまうほうが問題だ。
第4章:「怒り」は、自分を守ろうとする心の叫び
母がうそをつくとき、声を荒げたくなる自分がいる。でも、それは“怒り”というより“悲しみ”なんだと最近わかってきた。
「母がもう昔の母ではなくなっていること」への、さみしさと戸惑い。
それが怒りに姿を変えて僕の中からあふれてくる。死と生との狭間には生物の本質、言葉の無力さがあった。
だから最近は、怒りそうになったら一呼吸置いて、心の中で実況するようにしている。
「今、ムカついたな」
「においでイラついてる」
そう言葉にするだけで、感情が少し落ち着くこともある。
第5章:「介護は、愛の残業」
母のうんちに怒る自分を、僕は責めないことにした。
だって本音でしょ。キレイごとじゃない。リアルなんだ。
だけど、その本音に潰されないためには、「道具」「仲間」「逃げ場」が必要だと思う。
母はもう、僕が知っている母じゃない。けれど、かつて僕を育ててくれた“その人”が、いまこの体の中にいる。比喩的に言うと、母はすでに「死」を迎えている。魂はまた新しい肉体を探しうろつき始めた。きっと、僕たちの行動を見守り、何かを学ばせようとしている。
僕がやっていることは「愛の残業」なんだと思う。
報酬も評価もない。だけど、たぶんそれが“人間”ってやつなんじゃないかと思う。
終わりに:においも、怒りも、受け入れていい
介護の現場には、きれいな感情ばかりじゃない。 腹が立つこともある。逃げたくなることもある。でも、それでも続けてる。
僕は今日も母の紙おむつを替えた。 母は「してない」と言い切ったけど、おむつにこびりついたうんちを見て、他人事のような顔をした。
きっとこれからも、においに耐えられない日があるだろう。 でも、においごと、怒りごと、抱えていく。
それが僕なりの、母への最後の“ありがとう”なのかもしれない。