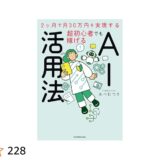AI小説創作で役割分担
50代も後半に差しかかった私は、いま改めて「小説家になる」という夢に挑んでいる。その相棒は、なんとAIだ。小説のアイデア出しはChatGPTに、プロットと本文執筆はClaudeに。そんな二人三脚で、現在私はあるSFビジネスファミリー小説を執筆中だ。
この物語は、感情を数値化・商品化し、それをエネルギー源として活用するという未来的ビジネスを軸に、現代社会に生きる父と娘の関係を描こうというものだ。効率を追い求めるビジネス社会の価値観と、非効率で不確かな「家族愛」という感情の間にある矛盾と共存。その葛藤を描くことで、読者に「人間らしさとは何か」を問いかけたいと思っている。
タイトル選びという試練
そんな中、最初に大きな壁として立ちはだかったのが「タイトル決定」だった。
私が最初に思いついたのは、「感情インフレマネタイズ」というタイトル。これは、自分でも「うまいこといったな」と思った。しかし、Claudeの反応は冷静そのものだった。ある意味、冷たかった。
彼は、良い点と懸念点を明快に列挙した。
- インパクトがある
- 感情の商品化というテーマが伝わる
- 現代性とSF性がある
一方で、
- カタカナが多く、一般読者に馴染みにくい
- 家族愛という要素が見えにくい
- 経済小説と誤解されるリスクがある
と指摘。代わりに、「感情の冷凍保存」や「湯気の向こう側」といった、文学性や感情に寄せた案をいくつも提示してきた。どちらかというとこれまでもビジネスマン目線で小説を執筆してきた私としては、少しやぼったく感じる案が出てきた。
私が描きたい小説の本質
だが、私としてはこの作品の本質は「ビジネスエンタメ小説」だと考えていた。家族はあくまで感情を揺さぶる装置であり、テーマは「感情を調整し、ビジネスや人生を成功に導く術」なのだ。その立場から、Claudeと何度もやり取りを重ねた。
「新人賞を狙うなら、家族愛を前面に押し出すべきだ」 「ただし、ビジネス的なサブテキストは残せる」
このような戦略的提案を受け、私は徐々にハイブリッド型の構成に舵を切っていくことにした。
たしかにこれまで私は自分の書きたいことを書くことに集中して作品を創作してきた。しかし、小説新人賞に求められているのは、これまで世の中に存在していない種類の作品だということを考えると、はなはだ不十分な創作活動だった。
いっそマーケットに自ら歩み寄り、その中で個性を出していくという新しい手法に転換するいいチャンスでもある。紙ベースの創作からネット系に転換するのも、まさに自己満足的な文筆活動からの脱却の過程でもあった。AIがその橋渡し役をしてくれるような気がした。
タイトルが決まった瞬間
そして最終的にたどり着いたタイトルが、
「家族愛の投資効率について」
だった。
このタイトルのポイントは、「家族愛」と「投資効率」という一見相容れない概念を掛け合わせている点にある。そして最後の「について」がミソだ。
当初私は「やぼったいのでは」と懐疑的だったが、Claudeは「その違和感こそが文学的な強みになる」と主張した。実際、学術論文のような客観性と、家族という感情的なテーマとのギャップが、読者の知的好奇心をくすぐる。この構造が、新人賞審査員にも刺さるとClaudeは主張するので結局、私もしたがうことにした。
タイトルは後にいくらでも変更できるのであくまで仮設定。しかし、このタイトルに沿って、私とAIとの創作ディスカッションが繰り広げられることを考えると、作品の質を決定する要素としては大変、重要なポイントになる。
AIとの対話が創作を深めた
Claudeとのやり取りの中で感じたのは、AIとの創作は決して「従属」ではなく「対話」であるということだ。
むしろ彼は、私の意見に安易に迎合せず、作品のテーマを深く掘り下げ、時に私を論破しようとまでしてくる。その真摯さに、私はAIへの見方を大きく変えさせられた。
ただ単に私の判断を褒めたたえるだけなら、AIでなくても出来る。批判も交えながら、目的達成のために最善の案を提案する心意気を私は感じたのだ。
今後の展望と共創の可能性
現在、第2章のプロット作成に入っている。「家族愛の投資効率について」はまだ仮タイトルだが、私にとってはAIと本気で向き合った成果のひとつだ。
これからこの物語が、どこまで進化するか。どこまで人間とAIの「共作」が可能か。今回の出来事で私はAIの見方を大きく変えた。とにかくディスカッションを繰り返すことと、ワードを慎重に選んで真剣に質問すること。
AIは人間ではないけれど、人間以上に紳士的に接する必要があるということも学んだ成果だ。
私と同じようにAIと共に何かを作ろうとしているあなたの参考になればと思う。