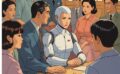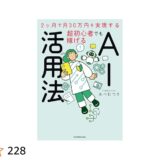AIは天才か、無能か。それとも粘り強さの鏡か?AIの使い方が少しずつ見えてきた編です
はじめに:AIがいれば小説は簡単に書ける?
AIを使って小説を書く――
そんな夢のような話を最初に思いついたとき、私は正直、ちょっと浮かれていた。
「AIに指示すれば、プロのような小説がスラスラ出てくるんじゃないか?」
27年新聞記者としてやってきた文章力に、AIの知識量と速度が加われば、もはや敵なし。そんな“無敵モード”を夢見ていた。
しかし、現実は甘くなかった。
出てくる文章は、どこかで見たような凡庸な文の羅列。
キャラに深みがなく、セリフもベタ。プロットにオチが見えすぎて、まるで既製品だった。
破綻からの再出発:プロットが必要だと知るまで
最初は「行き当たりばったりの執筆」を試みた。あえてプロットを定めず、自由に書き進めるというやり方だ。しかし、AIの出力はあまりにも“汎用”すぎた。
どこかで聞いたような会話、平板な心情、ありきたりな展開。
「これは、小説じゃなくて、パンフレットに書いたような作文だな……」
そこで私が参考にしたのが、山川健一氏、今井昭彦氏、葦沢かもめ氏共著の「小説を書く人のAI活用術」だ。詳しくは本文を見てほしい(アマゾンサイトを張り付けておいた)。
ある程度、大まかなビジョンを示し細かく指示しないと、AIの力が発揮できないということが、実例を示して書いてあった。
そこでまずビジョンを定めることから始めた。
「感情の資源化をテーマにする」――人間をもてあそぶ怒りや嫉妬、悲しみなど、AIにとっては不得手とする人間特有の感情。そのユニークさ、有用性を真正面から描こうと決めた(ちょっと壮大なテーマになってしまったが)。
次に目次の構成を何度も練り直した。本当に何度もやった。自分で最初からやったほうが早くできると一瞬、思ったが、僕にはできない発想が多々あったのでメリットの方を重視するよう自分に言い聞かせた。
全体で10〜15章。プロローグからエピローグまでの流れを設計し、それに応じてキャラクター設定を何度も作り直した。
例えば、主人公・風神連は冷凍食品開発者に。
その妻・沙也は、後に探偵的な役割を担う存在として再設計。
娘の灯は、言葉を失った少女。
さらには認知症の祖母、「AI遺言」としてコンピュータの中で生きる祖父、家庭のゴミを収集するAIロボット「ノムゾー」まで登場。
これらは全てAIが創出してくれたキャラクターだ。おそらく私ならこうした発想はしなかっただろう。
作業をしているときにふと思い出したのは、認知症をしている母との会話だ。コミュニケーションが完璧に成立していないのだが、結果的には求める結果を得ることができている。違う種類のコミュニケーションだと認識しないと続けることは困難だ。
こうして、ようやくAIが“面白い文章”を返してくれるようになった。
AIとの真の協働とは:“プロンプト職人”の誕生
AIは天才だ。ただし“相手がよければ”という条件付きで。
プロンプト(指示文)が曖昧なら、AIはすぐ凡庸な文章に逃げる。逆に、こちらが根気強く、丁寧に条件を伝えていけば、驚くような表現を返してくる。
「第三者視点を徹底して」
「感情はセリフや行動でにじませる」
「説明的な文は禁止」
「ハメット風のカメラ目線で」
特に条件を示して「5種類の案を出して」と回答に余白を与えるような質問をすると1つくらい当たりがでてくる。もしなかったら、canvaのマジック生成で何度もデザインをやり直させるように、「もう一度出しなおして」と注文すればいい。AIは「えー」とか言わずに、「いい提案です」とほめ返して淡々と再度出しなおす。そうすると案外、求めていた以上の提案が出てきたりする。
こういった注文を何十回と繰り返すうちに、AIが出す文が「共作した」と言えるレベルに達していく。
ついにプロローグへ:小説としての芯が見えた瞬間
舞台は中堅食品メーカー〈日本アグリフーズ〉。
下町に本社を置く老舗の上場企業だが、成長性がゆるやかな中小企業で大手食品メーカーのような勢いはない。冷凍カツ丼を“売り”にしている。
主人公の風神連は、ひと癖もふた癖もある開発マン。
“湯気の出る冷凍カツ丼”という奇想天外な商品を提案し、AI嫌いの上司と舌戦を繰り広げる。
そこに、マーケティング部の若手から「検証データに異常が出ました」と呼ばれ、会議室を出て行く――ここまでがプロローグ前半。
後半では帰宅中の電車内、妻からLINEで“娘・灯が言葉を発さなくなった”という報告が届く。
「娘の様子がなにかおかしい」と感じていた違和感が、診断によって“現実”として突きつけられる。
その不安を抱いたまま、電車の窓に映る疲れた自分の顔を見る連――そこでプロローグは幕を閉じる。
物語はようやく、動き出した。
気づいたこと:AIで小説を書くには“熱量”がいる
AIと小説を書く。それは“しつこさ”との戦いだった。
- こちらの意図を正確に伝えるプロンプト技術
- 自分の頭で構造を設計する力
- AIが得意なところと不得意なところを見極める判断
- AIはめちゃくちゃバカな所もあり、人間なら絶対にやらないような間違いをする。そうしたことを理解しないといけない
これらを何度も確認し、試行錯誤し、あきらめずに続けた。
すると、AIのアウトプットがこちらの「呼吸」に近づいてくる。
あるときは子供にさとすように、丁寧に前提条件とかも示す。これまでchatしてきた内容を再度、言葉で示して確認する作業も必要になる。
おわりに:AIは無能でも天才でもない。“鍛えれば育つ存在”だ
AIはあくまで“道具”ではある。だが、粘り強く付き合えば、人間の思考を引き出す知的な鏡にもなる。
プロローグを書き上げるまでにかかったやりとりは、数十ラウンドを超えた。
だが、そのすべてが、“より深く書きたい”という思いから生まれたやりとりだった。
小説は、結局、人間が書くものだ。
だが、AIと共に書いたからこそ、たどり着けたストーリー展開もある。
この“共作”のプロセスを、私はこれからも続けていこうと思う。
そして――このプロローグの先にある物語が、読者の心に届くことを願って。