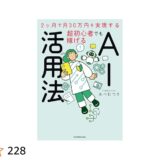この記事でこんなことが分かる⇒AIに好意的なポジションのプロの新聞記者が見た、AIの記者としての仕事評価
【はじめに:なぜAIを使い始めたのか】 新聞記者歴30年近くの私が、AIを本格的に使い始めたのは、ある元部下の一言がきっかけだった。詳しくは奮闘記・AIとシニア①(https://gomenne-ai.com/sinia-ai/)
その部下は今や人気ユーチューバーで、時代の流れに敏感な彼に「ChatGPTは、やばいくらい使える」と言われた。半信半疑で使い始め、小説のプロットを書かせてみた時、その速さと構成の巧みさに驚愕した。
まさかAIが文章の「創造」もできるようになっているとは。ここから私の奮闘が始まった。
第1章:AIで「楽になった」記者の仕事
AIを使ってみて、まず感じたのは「定型的な作業の効率化」だった。特に以下の作業で力を発揮した。
- あいさつ文やお知らせ文のテンプレート作成
- 会議録や講演の議事録要約
- インターネット情報の収集と要約
- 記事の見出し案、構成案の提示
- 一度書いた記事の続報でのプロット案作り
人間が時間をかけてやっていた作業が、AIなら数秒で終わる。しかも精度が高く、何度でも修正が可能。人間と違って文句は言わないし、修正を求めても、「鋭いご指摘」と、こちらを持ち上げ、再提出してくる。
まるで昭和の専業主婦のような忠実さ(昭和の女性、ごめんなさい、いい意味で使っています)、これは間違いなく記者業務の効率を押し上げる武器だと感じた。
第2章:「まだ任せられない」と感じた仕事
一方で、AIに任せて「違和感」が残った分野もある。
- 現場取材、特にもめごとや人間関係が絡む事件は不可能
- 混乱した状況での状況把握と感情の読解
- 調査報道、内部告発に基づく取材など
- ニュアンスのある言い回し、筆者の思いがにじむ原稿。情報を与えれば書くことは出来るだろうが、その手間があれば自分で書いた方が早い
AIは今のところ「素材を処理する」のは得意でも、「素材を見つけ、掘り下げ、自らニュースの視点や軸をしっかり持って書く」部分はまだ人間に軍配が上がる。
第3章:AIと人間記者の役割分担
これからの記者は「書く」ことよりも「見つける」「深く問う」ことが重要になるだろう。AIに出来ないことをやらなければならない。
記者会見でもステレオタイプの質問ではなく、取材対象者が顔をしかめるような厳しい質問を、国民の知る権利のために、国民代表としてぶつける必要がある。記者の資質がより問われる状況に入ってきた
- AIは資料整理、文法チェック、記事構成などを担い
- 人間記者はテーマ設定、取材交渉、濃密な取材、読者との共感構築、ネタ元との人間関係構築、複雑な記事の執筆に注力する
その分、記者にはより高度な「人間力」が求められる時代に突入する。
第4章:AIは人間記者を超えるのか?
近い未来において、AIが人間記者に並ぶ日が来るのか? 俺の予想では、定型的なニュース記事、決算報道、イベントレポートなどは、ほぼAIに置き換えられるだろう。 しかし、人間記者が優位なのは以下のような領域だ:
- 社会問題を発掘し、告発に踏み込む取材
- 当事者の声に耳を傾け、物語として届ける記事
- 感情・葛藤・人間の揺れ動きを描くルポルタージュ
AIは進化し続け、「共感」や「魂」の領域まで入り込んでくる可能性がある。更に俺が脅威と思っているのは、音源データをスピーディーに要約、分析し、いとも簡単に記事が書けるようになったときだ。記者が得る第一級の一次情報は、常に人間の口から出される声から入手される。
人間記者はレコーダーが装備された腕時計を常に持ち歩き、ストップウォッチのボタンを押すだけで、AIがある期間の音源を要約文字興し、要求する通りの文章に仕上げる。これが手軽でスピーディーにできるようになれば、AIの記者業務は一気に拡大するだろう。
これまで3人で手分けしていた取材、執筆が1人で出来るようになる未来はそう遠くない
そうした中でも人間記者が独自性を発揮できる領域はあるのか。「人間とは何か」を問う哲学が、より注目されることになると俺は見ている
終章:AIと共に記者として生きる
AIを使い始めて20日。俺はAIを恐れるよりも、相棒として受け入れる方が得策だと感じている。
記者はこれまで社会の鏡であり、声なき声の代弁者だったが、これからはAIができない複雑な取材や執筆をする「専門技術職」になる。AIを使いこなす技術が必要なのではなく、自分にしかない視点と情熱が大切になる。AIの進化は俺たちの想像を超えてくるのは間違いない。
俺は社会のAI化に遅れて参入した新聞記者だが、いまからでも遅くはないと信じている。これは「AIバブル」ではなく、人間社会の根本的な変化だと見ている。