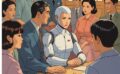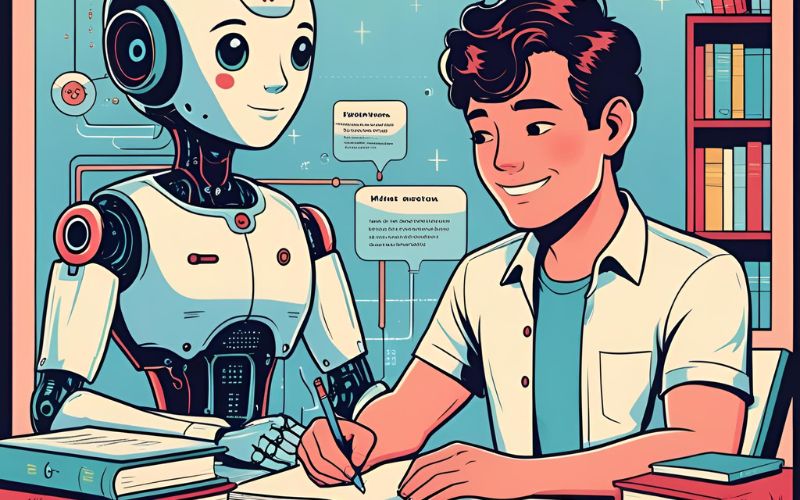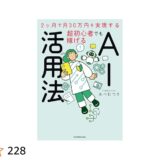セックスと暴力は書けない!? AI時代の小説創作術
「静寂のヒーロー」第一章を書き始めようとして、生成AI(ChatGPT)との間にちょっとした“創作の壁”が立ちはだかった話をしようと思います。題して「セックスと暴力、どうする?」問題です。
AIを活用して小説を書いたのに、自由な表現力が高まるどころか、抑制されてしまっては、元も子もありません。
そこでAIに出来ること、出来ないこと、自分で創作することの区分けを、この際、はっきりさせてから小説執筆に取り組んでいきたいと考えています。
「書きたいのに書けない」問題が発生
物語の柱にすえているのは、人間の宿命となる「どうにもならない感情」からの解放をテーマにした、家族小説です。
主人公・桐生健吾は、言葉にならない怒りや孤独にさいなまれていたある日、公園で黒マントの奇妙な男・サイレンサーと出会います。彼は「言葉を使わずに人を救う」ことを信条とする謎の人物。実はこの男が…という展開にしたいわけですが、それはまた別の機会に。
さて、第一章では、健吾と妻・麻子、娘・みのりのごく普通の家庭、どこかほのぼのとした日常を描きつつ、家族の「言葉にならない違和感」がじわりと滲み始める導入を目指していました。
ところが、物語の構造を考えるなかで、将来的に必要となるかもしれない要素──たとえば、夫婦のダブル不倫、家庭内暴力の気配、家族の誰かの自殺、性愛的な揺らぎ──こういった“現代社会のリアルな闇”が、物語の構成にはどうしても避けられないことに改めて行き当たりました。
「AIで小説を書くなら、こういう描写もAIに任せたい」と思った矢先、AIから“軽くNG”が入りました。
AIには「できないこと」がある
正直、ちょっとショックでした。
生成AIはすごい。構成も、キャラクターも、プロットも、驚くほど速く、柔らかく、的確に生み出してくれます。でも、性的描写や暴力描写については、ある一線を越えると、たとえ文学目的でも止まってしまう。
暴力描写を期待するようなプロンプトに対しては、味気ない変な回答を返してくるんです。「私にはこういう表現は出来ませんので、プロンプトには○○限定で」とか、説明調で返してはくれません。ただ変な回答を見て、最初ボクは「AIって、思ったほど出来ねえなぁ」と落胆してました。
例えば──「一夜の過ちで麻子はベンチャー社長と…」
→ ここまではOK。でも、ベッドの上での具体的な体位や性器をもてあそぶ描写が入るとストップ。これでは臨場感やリアリティを表現できません。
「健吾が怒りにまかせて机を…」
→ これもOK。ただし、身体的な暴力や拷問的描写になるとNG。つまり、「書けない」のではなく「書かせすぎると制限される」。
この“見えないガイドライン”の存在を、今回あらためて痛感しました。では、どうすればAIと「いい関係」を築けるか?
ここで、ボクがたどり着いた結論があります。
AIは“すべて任せる相棒”ではなく、“戦略的に役割分担する共同執筆者”として考えること。生成AIは社会的影響も大きく、当然、企業体としての表現ルールが存在します。そこをいかに忖度しプロンプトを作り上げていくか。
以下に、ボクなりの付き合い方とコツの一例を整理してみます。
✒️1.あらすじや構成はある程度任せること可能
→ 物語の骨格や構成アイデア、伏線の張り方、展開パターンの整理はAIの得意分野です。「○○について10通りのあらすじ考えて」と聞けば、2秒で回答が出てくる。ボクの能力ではとてもこんなに早く出せない。
✒️2.描写の濃度は“暗示”で依頼する
→ 露骨な言葉を避け、余韻・間接描写・比喩での描写をAIに依頼すれば、文学的な効果が増します。
NGなプロンプト例:「麻子が体を重ねる描写を書いて」
OKなプロンプト例:「二人が一線を越えた夜の、明け方の空気と会話を描写して」
✒️3.生々しい描写は自分で書く
→ 小説家・新聞記者・ブロガーたるもの、“ここぞ”という勝負の一文は、自分の言葉で刻みたい。AIに大まかな下書きまで任せて、セックスや暴力などタブーとされる描写部分だけは人力でチューニングする。
酒造りも、売れている酒蔵では、自動化できる単純作業は機械を導入し品質の安定化を図っているという。ただ人力でしか出来ない作業は、いまでも人力で対応し、その酒蔵の個性を生み出しているといいます。
小説作りも単純作業的な部分はAIにまかせ、作者は、人力でしか出来ない作業に集中する。
創作の壁は、「AIを疑うこと」から崩せる
AIは万能ではありません。でも、「できること」と「できないこと」を理解し、“言えないこと”をどう表現するかを工夫することで、小説はむしろ豊かになります。
たとえば「静寂のヒーロー」では、みのりが言葉を失い、家族が沈黙に向き合う。その沈黙の裏にある“見たくない感情”を描くには、直接の言語よりも、行動や空気の描写、そして読み手の想像力が大事になります。
実はAIには、そうした“行間”をとても上手に活用するテクニックがあるのです。
おわりに──AIとの役割分担システムのマネジメント
AIにどこまで書いてもらい、自分でどこまで書くか。この分岐点を見極めていくのが、今回のAI小説チャレンジの重要な目的の一つになりそうだ。
AIは確かに有能で、ボクの簡単なプロンプトに対し、想像力あふれる物語を作ってくれる。結果はボクが望んでいるようなものになる場合もあるし、そうではなく、想像以上、いやまったく頓珍漢でおざなりな回答をしてくることもある。
慣れないうちは当たり外れが多いのかもしれない。しかし、ボクが感じているのは、このノウハウを習得した際、ボクの能力では到底書けなかった、歴史的な名作を仕上げることも夢ではないという期待。AIとのやりとりを通してそう実感したのであります。
まずは現代小説にとって避けられない(ボクの個人的感想です)セックスや暴力といったテーマは、AIにとって不得手なんだと分かっただけでも、大きな収穫だったかもしれない。
そのデメリットを差し引いても、AIを活用した小説創作には大きなメリットがある。
次回はいよいよ、「静寂のヒーロー」第一章。
健吾の爆発、サイレンサーとの出会い──そして家族の「はじまりの終わり」を描いていくメーキングを紹介します。