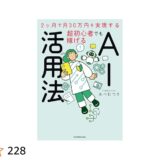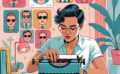※このページにはPRが含まれています

「分析ツール」と「キーワード選定」に振り回されて書く気力を失った方は必見ですよ
1. 自由な表現とSEOの「縛り」に戸惑う
「伝えたいことを書く」。 それは新聞記者にとって自然な行動だった。 だがWeb文章の世界に足を踏み入れると、そこには読者の「検索に当たる」ためのルールという重い足かせがあった。
書きたいように書くと、広大なweb世界の中で記事は埋もれる。
「 キーワードが入っていない」「見出しがストレートになっていない」と、この新世界の裁判官が判決を下してきそうだ。
そのため、表現したい内容を「ルール」に合わせなければならない、私にとっての「不自然さ」が生まれる。
自由に書くことが「驚くほど難しくなった」と感じた。
2. なぜSEOはこんなにもルールだらけなのか?
SEOの技術は日々進化している。 なかでも、最近のGoogleは「E-E-A-T」という基準で評価基準を分析しているようだ。
- Experience (経験)
- Expertise (専門性)
- Authoritativeness (権威性)
- Trustworthiness (信頼性)
この基準だけ聞けば、いかにも専門性や経験が重視され、未経験者や専門的教育を受けていない人は評価されように感じられる。
だが実際には、もっと技術的な別のルールも存在するようだ。
見出しの使い方、文章の長さ、ユーザー滞留時間、内部リンク。 これらは、すべて「機械的」に分析され、スコアに影響する。
ただし、「読みごたえ」や「表現力」といった、数字で採点できない指標は無視されがちなのだ。
長期保証付きで常時400種4000台の中古PCを販売【PC WRAP】3. 初心者がぶつかる分析ツールの壁
昔からある文章ルールで過ごしてきた中高年ライターは、ガイダンス(入門指導)もないままSEOの仕組みに振り回されると、すぐに壁にぶつかる。
Googleアナリティクスの解析スクリーンは、全体像を描いたレポートに見えるが、単純には読みとれない。
サーチコンソールは、どのページがどれだけ表示され、クリックされたかを数字で見せてくれる。
それじゃ答えは出ない。だから、もっと様々なツールにも手を出してみた。
- ラッコキーワード:関連キーワードをツリー形式で配列
- Ubersuggest:機械対応も良く、視覚的にもわかりやすい
- 人に聞く:これも最高の分析手段の一つ(最終兵器だ)
これらを試すうちに、SEОを突き詰めていけば、誰が「何を知りたがっているか」を簡易に探れることに気づいた。 これはまさに、現場の声を聞く取材に似ている。SEОとジャーナリズムの共通点が見えてきた。
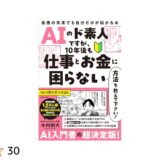
4. 記者の視点を武器にする考え方
分析は「解析」ではなく「観察」として解けば分かりやすいのかもしれない。
データをどう見るかは記者の知恵であるはず。 そこにニュースセンスや第一次情報をどう処理するかといった視点を組み合わせれば、「なぜそのキーワードなのか」を理解することができる。
SEOツールは「読者を知るネタ元」であり「究極の営業マン」なんだと思えば、最高の味方にすることができる。
5. 【結論】SEOは従うものではなく、使いこなすもの
私たち新聞記者にはデジタル化に対する被害妄想があるのかもしれない。
「SEO」と聞くだけで拒否反応を起こし、それ以上深く考えようとしなくなる。
SEOはあくまでも道具としてライターが使いこなすものであって、そのルール全部を守る必要はない。
伝えたいことを「検索されやすい形で」届けるという目的さえはずさなければ、人それぞれのさじ加減、活用方法があっていいのだと思う。
SEOをどう使いこなすかも、またそのライターの書く文章の個性になる。
表現するために、SEOを利用する。 それは、「毎日の記事を読んでくれる読者を知るための手続き」であって、直接表現を制限するものではないのだ。