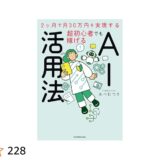※このページにはアフィリエイト広告が含まれます
はじめに
かつて「人間関係にやたらうるさく、高給取りで働かない」と揶揄された昭和世代が、生成AIという文明の利器を手に、令和の時代に復活の兆しを見せている。誰もがスマートフォンを操り、AIを活用する現代にあって、もっともAIと縁遠いと思われていた世代が、むしろその“使いこなし”において意外な適性を発揮しているというのだ。

まだまだやってやるぜ!という昭和世代に読んでほしい
これはただのノスタルジーや願望ではない。事実として、各業界で昭和世代がChatGPTなどの生成AIを活用し、再び脚光を浴びる事例が報告されている。俺自身、「マスゴミ」と若者に避難される新聞業界の現役だが、AIを武器に「新聞記者2.0」を実践し始めている。
経験×AIの時代へ
生成AIの登場により、「情報を知っているだけ」「調べられるだけ」では価値がなくなりつつある。代わって求められるのは、現場で培った知恵や判断力。これはまさに、昭和の現場で泥臭く働いてきた世代の十八番ではないか。
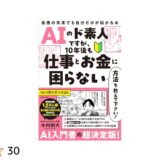
「経験の蓄積」がこれから求められる
たとえば、ある住宅会社では、展示会の企画案を若手社員がAIの助けも借りて練ったが、課長の求めるニュアンスとはどこかズレていた。そのズレの正体は「経験」だった。コロナ禍で現場の空気を吸ったことのない若手にとって、展示会のリアルな感覚はつかみきれなかったのだ。これが唯一無二の他社と差別化できるコンテンツなのだ。
そこでベテラン課長が、自らChatGPTを活用して企画案を作ったところ、あっという間に納得のいく案が完成した。パソコンは苦手で資料作りは部下にまかせていたが、ChatGPTは部下に投げかけるような言葉で指示を与えるだけで答えが返ってくる。経験のフィルターを通した指示がAIに与えられたことで、AIは見事に補完役を務めたのだ。
ChatGPTは“気を使わなくていい部下”?
「何度やり直しさせても文句を言わない」「感覚的な話も形にしてくれる」──こうした理由から、部下指導が苦手だった昭和世代の上司が、ChatGPTを最強の補佐役とするケースも増えている。ChatGPTへの指示はプロンプトと呼ばれる質問文で行われるが、何度も質問が繰り返せるため、下手な質問でも大丈夫。「どういうことを聞きたいですか」とChatGPTが何度も聞き返してくれる。「うぜぇ」なんて絶対に言わない。
ある鉄鋼メーカーでは、人事関係の業務改革案を若手が出したものの「通り一遍」の内容に終わった。そこでベテランがChatGPTと一緒に案を練り直した結果、経営層も納得の改革案ができあがったという。AIと対話を重ねる中で、自分自身の判断基準や経験が引き出されていくというプロセスが、昭和世代にはハマるのかもしれない。
インターネットの海でも復活の兆し

noteやYouTube、個人ブログでも、昭和世代がChatGPTを駆使して情報発信を始める事例が増えてきた。特に「昔取った杵柄」にAIの力を加えて副業化する流れは顕著だ。俺もAIを活用しこのブログを書いているし、webライターの下請け業務をしている。AIがなかったらとても副業の短時間ではこなせなかっただろう。
AI活用で月収が2倍になったという体験談や、ライティング業務でChatGPTをドラフト作成に活かして時短と質の向上を両立させた話など、希望が持てる話があふれている。そしてその多くは、「AIに任せっきりではなく、自分の経験や価値観を反映させることがカギだ」と語る。
まさに「AI×経験=再評価」という図式が、現実になりつつある。
俺たちの時代、また来るかもしれない
この流れを見て、現役の新聞記者である俺は直感した。これは「新聞記者2.0」の幕開けではないかと。AIの時代に、かつて取材現場を駆け回った感性と経験を活かし、紙面とは違った新たな媒体──例えばブログや動画、音声配信──で再び「伝える」役割を担う時代が来ている。
記事の執筆も言い訳ばかりしてなかなか原稿が出てこない部下にまかせるのではなく、ある程度の情報を入れてAIに書いてもらった方が早いし的確だ。
俺も今、クラウドワークスでライティングの仕事をしながら、ChatGPTと共にブログ運営に挑戦している。「昭和の超文系記者がAIに挑戦する」を通じて、同世代の人々に「遅くないぞ、まだ俺たちの出番はある」と伝えたい。
昭和世代は「遅れている」わけじゃない
AIは「うまく質問できる人」にこそ力を貸す。これは裏を返せば、「現場を知っている人」や「具体的な課題を持つ人」が最強だということだ。昭和世代の武器は、まさにそこにある。
私たちは、時代に遅れたのではない。むしろ、時代が私たちの経験に追いついてきたのかもしれない。これからは、「経験を語る力」と「AIを使いこなす技術」の両輪が求められる。その最前線に、昭和世代が立っているのだ。
だから私は声を大にして言いたい──「俺たちの時代、まだ終わっちゃいないぞ」と。